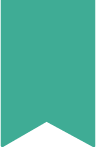今回教えてくれるのは、エルザ動物病院グループに所属し、ペットの問題行動の相談を受け付ける行動科の愛玩動物看護師で、子犬のしつけなどを行うパピーライフ指導・認定動物看護師の井口由加さんです。
井口さん、よろしくお願いします。

ペットの習性として拾い食いはよく聞きますが、何か原因があるのでしょうか?

看護師
もともと犬は気になるものがあれば臭いを嗅ぎ、口に入れて、食べられるものかどうかを確認する習性があります。
例えば、子犬のころに異物を口の中に入れた姿を飼い主が見た時、「飲み込んでしまっては困る」と思い、無理やり取り上げるような行為が続くと、
犬も「口に入れた物を取られまい」と飲み込んでしまうことがあります。
その結果、「食べてしまえば取り上げられない」と学習(負の強化)してしまうことが多いです。

質問者は食フンについても悩んでいます。家庭で試せる対処方法はありますか?

看護師
食フンを防ぐ方法として、愛犬が排便中、声をかけずに、いくつかフードやおやつを目の前に置いてみましょう。 それを愛犬が食べている最中、静かに排泄の処理をしてください。 飼い主のリアクションが大きいと「取られまい」と思い、余計に急いで食フンする子が多いです。

散歩中の拾い食いについてはどうでしょうか?

看護師
散歩中の拾い食いはリードコントロールで対応できると思いますが、拾い食いしないようにリードを引っ張り過ぎると、
ワンちゃんは嫌な気持ちになりますよね。
その場合は、散歩中に定期的にペットの名前を呼び、目が合ったらご褒美をあげてください。
名前を呼ばれて飼い主に注目すると「良いことがある」と学習させるといいでしょう。
このトレーニングを散歩中に歩きながら行うことにより、「何か落ちている」と飼い主が気づいたら、名前を呼ぶことで別の場所に誘導しやすくなるのもポイントです。

ワンちゃん本来の習性とどのように向き合っていくのかが大切ですね!家族以外を見て吠えてしまう癖も同じでしょうか?

看護師
よく飼い主側から「犬の無駄吠え」と言われますが、ワンちゃんにとって吠えること自体は正常な行動です。
吠える理由としては、恐怖、警戒、縄張り主張、興奮、欲求、痛みなど、さまざまな原因が挙げられます。
状況やボディランゲージなども含めて、なぜ吠えているのかを考えてみましょう。

ただ注意するのではなく、原因を一緒に考えてあげるのがポイントですね。

看護師
例えば、飼い主の食事中に吠えたら食べ物を分けてもらえた時。これはワンちゃんにとって欲求が通ったと学習(正の強化)されます。
逆に、訪問客に吠え続けたらその人が帰ったという状況。これは、縄張りを守れたと学習(負の強化)します。
このほか、インターホンがなって飼い主が興奮したから一緒に興奮して吠えた時。ペットのことを注意しようと見つめても、
ワンちゃんにとっては「注目してもらえた」と受け取ってしまいます(正の強化)。散歩中に前から自転車が向かってきた時、
ワンちゃんからは怖いと思うこともありますよね。この時は怖くて吠え続けて逃げていったと学んでしまうことがあります(負の強化)。

吠え続けることで、自分の要望が通ると思ってしまうのですね・・・。ワンちゃんとの正しい向き合い方はありますか?

看護師
大事なのは、“吠え続けさせない”ことです。インターホンなどの物理的な音がある場合は、ワンちゃんが「インターホン=吠える」の認識にならないように、インターホンの音を変えたり、飼い主ができるだけ冷静に行動したりすることを心がけてください。
また、インターホンを鳴らして、「ハウス」の指示を出し、ワンちゃんがそこで待つことができたら、ご褒美をあげるのもおすすめです。状況や犬の行動、性格に合わせて修正方法を考えていきましょう。
当院ではペットの問題行動の予防や相談を受け付ける行動科や、子犬のしつけをトレーニングするパピーライフ指導もあります。
ぜひ公式HPを見て、受診の参考にしてください。
エルザ動物病院ではペットの健康や生活環境に関する悩みを募集中!
➡︎質問フォームはこちら

「エルザ動物病院グループ」は、動物たちの健康と飼い主との豊かな暮らしを守るため、「動物の幸せを第一に考える」診療を提供している。
一般診療や予防医療、健康診断をはじめ、ペットフードの相談やしつけセミナーの開催、さらには専門科診療やMRI・CTなどの高度医療機器を活用した検査、夜間救急診療まで幅広く対応。
姫路・加古川・神戸・たつのを中心に病院を展開し、グループネットワークを活かした地域密着型の動物医療サービスを提供している。
公式ホームページはこちら
病院一覧はこちら